
 |
| ◆主な概要 The main outlines |
| ここでは熊本県熊本市について紹介していきます。熊本市は九州中央に位置する、地方中核都市となっています。人口は約70万人となっており、福岡市(138万)・北九州市(100万)に次ぐ九州第3の都市です。地理的に九州の中心なので戦前は九州の首都として発展を続けてきました。江戸から明治になり、熊本洋学校、陸軍幼年学校、官立第五高等学校など、様々な学校の設立や鎮西鎮台が設置され、学都・軍都としての機能を備え、文字通り九州の首都だったわけですが、戦後の昭和47年、福岡市が政令指定都市に昇格したのを機にそのほとんどの首都機能が福岡市へと移転してしまいました。今でも農政・郵政・財務局や森林監督署など、約16の諸機関が熊本に残っています。熊本の都市としての特徴ですが、県総人口185万人の約3分の1の人口が熊本市を中心とした熊本都市圏に集中しています。市域人口約70万を擁する都市ですが、上水道は全てが地下水で賄われており、上水道の質の高さは国内でも有数のものとなっています。(65L/\10)平成8年には中核市に移行、現在でも順調に人口が増加しています。地価も地方都市としてはかなり高く、政令指定都市と同等のものとなっていたりします。市の基幹産業はサービス業(2次)と農業(3次)となっており、農業粗生産額は全国第5位となっています。商都としての顔とは裏腹に農業都市としての顔も伺えます。工業都市としての顔ですが、熊本市よりも周辺町村の方が工業は盛んだったりします。阿蘇の豊かな伏流水と空港が近いのもあり、隣接する菊池郡菊陽町や大津町、上益城郡益城町に大規模なIC工場が多数立地しています。熊本市はこれから九州新幹線全線開業に向け、九州第3の政令指定都市を目指すと言う動きが出ていますが、やっぱりなかなか上手くは行っていないようです。10年以内に迫った九州新幹線全線開業とこれまで以上に深刻となる高齢化や少子化の波が押し寄せるとなると、やっぱりこれから必要なのは、これまで以上の都市としての魅力です。一方では道州制導入なども囁かれており、都道府県の概念が無くなると言うことになると、県庁所在地としての顔も失うことになります。(州都を目指すと言った動きも出ているようです)熊本にとってはこれからの10年がこれからの運命を左右する大事な時期となるかも知れません。ちょっと長くなりましたが、説明と致します。 |
| ◆数字で見る熊本市 Kumamoto-city seen numerically |
| 市域面積 | 266km2 |
| 市域人口 | 約70万 |
| 都市圏人口 | 約105万 |
| 市内最高地価 | 1,830,000(\100万/m2以上) |
| 都市インフラ | ハード面が今一歩 |
| 主幹産業 | 農業、サービス業 |
| 都市規模 | 中核市 |
| ◆難読地名 The difficult name of a place |
| これは全国諸都市でも同じことが言えるかも知れませんが、異様に難読地名が多いのも特徴です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊本市外だと、山鹿市の「来民(くたみ)」。菊池郡合志町の「幾久富(きくどみ)」「竹迫(たかば)」。八代市の「海士江町(あまがえまち)」などもあります。 |
| ◆市内写真集 City photographs |
 熊本市内の交通を紹介しています。 熊本市内の交通を紹介しています。 |
 ◆熊本交通センター 熊本は軌道系交通より、どっちかと言うとバスの方が都市交通として成立しています。交通センターにはくまもと阪神百貨店と地下街が併設されており、1日に約16万人の利用があるとのことです。バスの発着数は1日に約6,200本となってます。 |
◆LRV 1997年に日本で初めて導入された、超低床車両です。「誰もが使いやすい」がコンセプトの路面電車は、車社会を抜本的に見直すために、「LRT」という、次世代の都市交通システムとして欧米ではどんどん復活を遂げています。この車両の導入を機に、日本国内でも路面電車が見直され始めました。熊本市交通局では現在5編成が運行されており、今後も導入を進めて行くとのことです。これから熊本電鉄と市電の相互運転を実現し、熊本都市圏を南北に縦断する、国内2番目のLRT網が整備される予定です。(2006年4月29日に国内初のLRT線、「富山ライトレール」が開業します。) |
 ◆熊本市電 熊本と言えば路面電車を連想する方もいらっしゃると思います。1924年(大正13年)8月1日開業以来、市民の足として活躍を続けています。戦後の高度経済成長における、モータリゼーションの発達によって一時期都市交通としては見捨てられようとした時期がありましたが、今日では見事に市民権を獲得しています。 |
 ◆JR鹿児島本線熊本駅 バスの方が都市交通として熊本では確立していますが、軌道系交通も健在です。1891年(明治24年)に当時の九州鉄道が熊本まで開業しました。開業当時は「熊本駅」ではなく「春日駅」と呼ばれていました。春日駅と呼ばれていた頃、この辺りは飽託郡春日村のボーブラ畑(かぼちゃ)の中にありました。中心街からは約2kmほど離れています。 |
 熊本市内で開催されるお祭りの紹介です。 熊本市内で開催されるお祭りの紹介です。 |
 ◆藤崎八旛宮秋季例大祭 肥後っこには馴染みの深いお祭りで、約1,000年ほど前から続いていると言うことです。60もの団体が出場し、各団体ごとに馬がお供します。出場団体の多くは高校の同窓会や地区の自治会から成っており、毎年楽しみな祭りでもあります。期間中は市中を馬が暴れ回ります。 |
 ◆火の国まつり 毎年8月11日〜13日の3日間開催される、熊本の夏の風物詩の一つです。1日目はオープニングイベント、2日目は市内目抜き通りでの総踊り、3日目のフィナーレは江津湖で1万発の花火大会が催されます。期間中は市電の花電車も運行され、祭りに華を添えます。 |
写真がないので掲載していませんが、この他には本妙寺の屯写会などがあります。
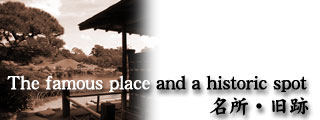 市内にある、主な名所・旧跡を紹介しています。 市内にある、主な名所・旧跡を紹介しています。 |
| ◆熊本城 Kumamoto castle |
 ◆大天守・小天守 熊本城と言えば、このアングルが一番お馴染みではないでしょうか。姫路城、名古屋城と並び、日本三大名城となっています。非常に堅牢な城郭となっており、難攻不落の城として知られています。1877年(明治10年)の西南戦争時も54日間一人の侵入者もなく、絶え続けました。西南戦争後には鎮西鎮台が置かれました。軍都熊本の象徴でもあります。 |
 ◆宇土櫓内部 光の具合がよかったので思わず撮影してしまいました。宇土櫓は西南戦争のときも焼けずに築城当時の雰囲気を今に伝えています。明治期に一度解体・補修されましたが、それ以外は手付かずのままです。とても雰囲気がいいので、寝転がりたくもなります。2階と3階には誰もいないので昼寝にはぴったりかもしれません。と言うより、昼寝に最適の場所です。春は特にオススメ。 |
 ◆城内の石垣、武者返し 熊本城の象徴でもある、石垣です。石垣の積み方は加藤清正独特の工法で、正に軟弱な茶臼山の地形を熟知していたことを物語ります。石垣の長さもとてつもないものであり、加藤清正が経験し、得た全てが生かされています。 |
 ◆西大手櫓門 城内各所には様々な門があり、明治期までは全てが残されていましたが、西南戦争や戦後進駐軍が占領したときにそのほとんどが撤去されてしまいました。現在、熊本市が復元整備を進めています。(一口一万円で城主になれます。) |
◆加藤清正 熊本の城下町を作った加藤清正の像です。又の名を「土木の神様」と言い、熊本の地形を大幅に変えた人でもあります。出身は尾張国中村村、現在の名古屋市中村区です。 |
 ◆大天守からの熊本市街地の眺望 こうして見ると、熊本には高層建築は一切ありません。昭和50年代に市の都市景観条例が制定され、熊本城から阿蘇の眺望を確保するため、熊本城の石垣より高い建物を建ててはならないと言う決まりが設けられたためです。街全体が景観を作り出しています。 |
| ◆加藤清正菩提寺、本妙寺 Kiyomasa Katou,The family temple of "HONMYOJI" |
| ◆水前寺成趣園(すいぜんじじょうじゅえん) Suizenji park |
 ◆水前寺成趣園その1 観光パンフレットにも掲載されている、お馴染みのアングルです。歴史は大変深く、加藤家の時代にさかのぼります。戦後熊本動物園が現在地に移転する前はこの水前寺成趣園の中に動物園が併設されていました。 |
 ◆水前寺成趣園その2 園内の写真です。市内各所から阿蘇の伏流水が湧き出ていますが、その中でもここの水は特に清冽です。と言うより飲めます。この一帯は水前寺・江津湖公園となっており、ここから湧き出た水は、江津湖→加勢川・緑川へ注ぎ、やがて有明海へと至ります。 |
 ◆出水神社 水前寺成趣園内にある、出水神社です。この神社は学問の神様と詠われており、受験生が多く訪れます。 |
| ◆北岡自然公園 Kitaoka nature park |
 ◆北岡自然公園 熊本駅に程近い、花岡山のふもとにある公園です。「熊本藩主細川家墓所」として国指定の史跡に指定されています。自然の景観を生かした枯山水庭園やバラ園があり、市民の憩いの場として親しまれています。 |
 熊本市の街並みを紹介しています。 熊本市の街並みを紹介しています。 |
| ◆市中心部 Downtown |
 ◆熊本市庁舎・市会議事堂 熊本市の中枢、市役所と市会議事堂です。現在のようになったのは1981年(昭和56年)です。 |
 ◆びぷれす熊日会館・ホテル日航熊本 市街地の再開発事業の一つとして、2002年にオープンしました。中に入っている現代美術館は国内初の公立の美術館でもあります。 |
 ◆現代美術館内部 びぷれす熊日会館内の写真です。中は落ち着いた感じになっています。寝転がりながら本を読むことも出来ちゃいます。様々な催しがいつも開催されており、いつ行っても楽しいところです。子供連れでもいいように、プレイルームも完備。 |
 ◆上通(かみとおり) 熊本市の中心街の一つ、上通です。戦前より学生街として発展を続けてきました。老舗が沢山並ぶ通りでもあります。パリのオルセー美術館がモデルになっており、どこか大人の雰囲気漂う、落ち着いた感じになっています。 |
 ◆下通(しもとおり) 熊本市の中心街の一つ、下通です。とても開放感のある作りになっています。上通とは違い、若者の通りと言った感じが漂います。 |
 ◆小泉八雲旧居 小泉八雲から松江から赴任してきて最初に住んだ家です。現在でも当時のまま残されており、周囲は公園として整備されています。 |
 ◆水道町 熊本市内で一番交通量の多い交差点です。繁華街の東端に位置し、国道3号・県道28号・市電健軍線が交差します。背後の建物はテトリア熊本です。 |
 ◆長塀通り 坪井川を隔てた、熊本城の東側に位置する通りです。石畳が落ち着いた雰囲気を醸し出します。火の国祭りのときになると、屋台が並びます。手前は市役所方面です。 |
 ◆オークス通り 上通の裏手にある、通りです。名前の由来は大きな楠があるところから来ているようです。周囲には個性的なショップが軒を並べています。 |
 ◆シャワー通り 何故か夜に撮影した写真ですがご了承ください。太陽の光がさんさんと降り注ぐと言う意味からシャワー通りと名付けられています。 |
 ◆通町筋 熊本市のメインストリート、通町筋です。休日ともなると人で溢れています。熊本でも一番地価の高いところでもあります。 |
 ◆日本郵政公社九州支社(旧九州郵政局) 九州の郵政業務を総括している、郵政公社の建物です。この建物は案外古く、1960年代に完成したとのことです。 |
| ◆旧市街 The old street |
 ◆旧第一銀行熊本支店 この建物は1919年(大正8年)に竣工しました。熊本には古い建物が数多く残っています。前の通りは唐人町通りとなっており、熊本市の旧市街となっています。老舗の問屋さんが並んでいます。 |
 ◆新町 こちらも熊本市の旧市街、新町の風景です。丁度真ん中にある建物は長崎次郎書店の建物で、国指定の重要文化財になっています。加藤清正が熊本に入国した際、清正を慕って付いてきた人たちが作った町人町となっています。 |
 ◆吉田松花堂 同じ新町にある、吉田松花堂の建物です。とてもいい雰囲気を醸し出しています。 |
| ◆江津湖周辺 The circumference of a Ezu lake |
 ◆熊本県庁舎・県警本部・県会議事堂 熊本県の中枢、県庁です。元々は桜町の交通センターのところにありましたが、昭和40年代に現在地に移転してきました。 |
 ◆上江津湖 市街地の真ん中にありますが、かなり静かな場所となってます。1日約40万トンもの水が湧き出る日本有数の湿地です。 |
 ◆加勢川沿いの風景 上江津・下江津に流れ込む加勢川沿いの風景です。光の具合がよかったので思わず撮影しました。水も綺麗なので水遊びには最高の場所です。 |
◆江津の風景 江津湖は湿地なのでいろんな水鳥を見ることが出来ます。 |
ここには掲載しきれていない写真もありますが、紹介を終わります☆彡
画像及び文章の無断転載を禁じます
(C)1978-2004 Kumamoto Daiichi Leo Club
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
